お正月の初詣や縁起物として馴染み深い「七福神」。その名前一覧や、それぞれがどんな神様でどんなご利益があるのか、気になったことはありませんか?恵比寿様や大黒様は知っていても、全員の名前や特徴をスラスラ言える人は意外と少ないかもしれません。
この記事では、七福神の名前一覧はもちろん、各神様のご利益、特徴、知っているとおもしろい由来や豆知識を徹底的に解説します。この記事を読めば、七福神巡りや普段のお参りが何倍も楽しくなるはずです。
1. 七福神の名前とご利益がひと目でわかる一覧表
七福神について詳しく知りたいけれど、まずは手っ取り早く名前とご利益を知りたい、という方も多いでしょう。下記に七福神の名前、読み方、代表的なご利益、特徴を一覧表にまとめました。
ぜひ、お正月の話題づくりや、お子さんへの説明などにご活用ください。
| 神様の名前 | 読み方 | 代表的なご利益 | 特徴・持ち物 |
| 恵比寿 | えびす | 商売繁盛・大漁追願 | 釣竿と鯛 |
| 大黒天 | だいこくてん | 五穀豊穣・財福 | 打ち出の小槌・大きな袋 |
| 毘沙門天 | びしゃもんてん | 勝負運・厄除け | 甲冑・宝塔・槍 |
| 弁財天 | べんざいてん | 学問・芸術・金運 | 琵琶 |
| 福禄寿 | ふくろくじゅ | 子孫繁栄・長寿 | 長い頭・杖・経典 |
| 寿老人 | じゅろうじん | 長寿・健康 | 杖・桃・鹿 |
| 布袋尊 | ほていそん | 家庭円満・千客万来 | 大きな袋・太鼓腹 |
2. そもそも七福神とは?知っておきたい3つの基本知識
七福神の名前とご利益を一覧で確認したところで、次はその背景を少し深掘りしてみましょう。「そもそも七福神とは何なのか?」という基本的な知識を知ることで、より一層理解が深まります。
ここでは、七福神を理解する上で欠かせない「由来と歴史」「国際性」「七という数字の意味」という3つの基本知識を分かりやすく解説します。

(1)七福神信仰の由来と歴史
七福神信仰は、室町時代の末期に京都で始まったとされています。 当時の京都の町衆(商工業者など)の間で、様々な福の神をまとめて信仰する風習が生まれ、それが次第に「七福神」という形で定着していきました。
江戸時代になると、幕府がこの信仰を奨励したこともあり、日本全国へと広がっていきます。特に正月に七福神を祀る寺社を巡拝する「七福神巡り」が庶民の間で大流行し、今日まで続く文化として根付いたのです。このように、七福神は民衆の中から生まれた、身近で親しみやすい信仰といえます。
(2)国際色豊かな神々の集まり
七福神の大きな特徴は、様々な国の神様が集まった「国際色豊かなドリームチーム」であることです。 メンバーの出身地を見てみると、インド由来が3柱、中国由来が3柱、そして日本古来の神様が1柱という構成になっています。
- インド出身: 大黒天、毘沙門天、弁財天(ヒンドゥー教や仏教の神様)
- 中国出身: 福禄寿、寿老人、布袋尊(道教の仙人や実在の僧侶)
- 日本出身: 恵比寿(日本の古来の神様)
異なる宗教や文化の神々が、日本の「神仏習合(しんぶつしゅうごう)」という柔軟な精神性の中で一つにまとめられ、福をもたらす存在として一緒に祀られている点は、非常に興味深い文化です。
(3)なぜ「七」という数字なのか?
「七」という数字は、仏教の経典にある「七難即滅、七福即生(しちなんそくめつ、しちふくそくしょう)」という言葉に由来すると言われています。 これは、「七つの災難がたちどころに消滅し、七つの福がたちどころに生まれる」という意味を持つ、大変縁起の良い言葉です。
この教えに基づき、7柱の神様をお参りすることで、あらゆる災いから逃れ、多くの福を授かることができると考えられました。また、七は「ラッキーセブン」のように世界中で幸運の数字とされることも多く、人々にとって覚えやすく、親しみやすい数だったことも、七福神信仰が広まった一因でしょう。
3. 【神様別】七福神 全7柱の名前・ご利益・特徴を解説
七福神の基本的な知識を押さえたところで、いよいよ各神様のプロフィールを詳しく見ていきましょう。ここからは、個性豊かな七福神のメンバーを一人ずつ、名前の由来やご利益、見分け方を詳しくご紹介します。
それぞれの神様の背景にある物語を知ることで、今まで何となく見ていた置物や絵が、まったく違って見えてくるはずです。
(1)恵比寿
七福神の中で唯一、日本古来の神様である恵比寿。にこやかな「えびす顔」で知られ、私たちに最も身近な福の神の一人です。
①主なご利益
恵比寿様の最も代表的なご利益は「商売繁盛」です。 また、元々は漁業の神様であったことから「大漁追願」のご利益でも知られます。
海から幸をもたらす神様として、漁師たちからあつい信仰を集めました。その信仰が時代と共に広がり、市場での取引の成功、つまり商売繁盛の神様としても崇められるようになったのです。農業の神として「五穀豊穣」のご利益もあります。
②特徴と見分け方
恵比寿様を見分ける最も簡単なポイントは、右手に「釣竿」を持ち、左脇に大きな「鯛」を抱えている姿です。 この姿は、恵比寿様が漁業の神様であることを象徴しています。
鯛は「めでたい」に通じる縁起の良い魚であり、お祝いの席に欠かせません。恵比寿様が持つ釣竿と鯛は、まさに「福を釣り上げる」姿そのものと言えるでしょう。優しく微笑む表情も大きな特徴です。
③由来と豆知識
恵比寿様の由来には諸説ありますが、日本神話に登場するイザナギとイザナミの子である「ヒルコノミコト」や、大国主命(おおくにぬしのみこと)の子である「コトシロヌシノカミ」と同一視されることが多いです。
にこやかで穏やかな笑顔を表す「えびす顔」という言葉は、恵比寿様の表情が語源となっています。 恵比寿様は耳が遠いという伝承もあり、お参りの際には拝殿の横にあるドラを叩いて存在を知らせる風習が残る神社もあります。
(2)大黒天
大きな袋を肩にかけ、米俵の上に乗る姿で知られる大黒天。その福々しい姿から、恵比寿様と並んで絶大な人気を誇る福の神です。
①主なご利益
大黒天の主なご利益は、食物に困らない「五穀豊穣」と、金運アップの「財産・福徳」です。 また、子沢山な神様であることから「子孫繁栄」のご利益もあるとされています。
元々はインドの戦闘神でしたが、日本では農業や財産の神様として信仰されるようになりました。特に厨房や台所に祀られることが多く、「家の食を司る神様」として大切にされてきました。
②特徴と見分け方
大黒天は、右手に「打ち出の小槌」、左肩に「大きな袋」を背負い、「米俵」の上に乗っているのが特徴です。 打ち出の小槌は振れば願いが叶うとされる宝物で、財宝を生み出す象徴です。
大きな袋には、人々の苦労を代わりに背負うための「七宝(金、銀、瑠璃など)」が入っていると言われています。米俵は豊かな実りを表しており、これ以上ないほど縁起の良い姿をしています。
③由来と豆知識
大黒天のルーツは、インドのヒンドゥー教の破壊神「シヴァ神」の化身である「マハーカーラ」です。 マハーカーラは黒い身体を持つ恐ろしい姿の戦闘神でしたが、仏教に取り入れられ、寺院の守護や豊穣の神としての性格を持つようになりました。
日本に伝わると、名前の「大黒」が日本の神様「大国主命(おおくにぬしのみこと)」の「大国(だいこく)」と同じ読みであることから、二つの神が一体化(神仏習合)し、現在のような温和な福の神の姿になったのです。

(3)毘沙門天
七福神の中で唯一、甲冑(かっちゅう)を身に着けた勇ましい姿の毘沙門天。その凛々しい姿から、勝負運や厄除けのご利益で信仰されています。
①主なご利益
毘沙門天の最も知られるご利益は、戦いや勝負事の勝利を願う「武運長久(ぶうんちょうきゅう)」です。 現代では、スポーツの試合や受験、ビジネスでの成功を願う人々に信仰されています。
また、邪気を払う強い力を持つことから「厄除け」の神としても知られます。さらに、元々は財宝の神様でもあったため、金運アップの「財宝来福」のご利益も授けてくれる、頼もしい存在です
②特徴と見分け方
毘沙門天は、武将のような「甲冑」を身に着け、片方の手に仏の教えが詰まった「宝塔(ほうとう)」、もう一方の手に邪気を払う「槍(やり)」や「宝棒(ほうぼう)」を持っているのが特徴です。
厳しい表情で邪鬼を踏みつけている姿で描かれることも多く、七福神の中でもひときわ力強く、見分けやすい神様と言えるでしょう。その姿は、私たちをあらゆる災難から守ってくれる守護神のようです。
③由来と豆知識
毘沙門天のルーツはインドの財宝神「クベーラ」で、仏教では仏法を守護する「四天王」の一人、「多聞天(たもんてん)」として知られています。 四天王として北方を守護する際は多聞天、単独で祀られる際は毘沙門天と呼ばれることが多いです。
戦国武将の上杉謙信が自らを毘沙門天の生まれ変わりと信じ、厚く信仰していた話は有名です。その武勇にあやかり、多くの武士たちから信仰を集めました。
(4)弁財天
七福神の中で唯一の女神である弁財天。音楽や芸術、学問の才能を授けてくれる神様として、古くから多くの人々に信仰されています。
①主なご利益
弁財天の主なご利益は、音楽や絵画などの「芸術」や「学問」の才能開花です。 そのため、芸事に関わる人々や、試験合格を目指す学生から篤い信仰を集めています。
元々は水の神様であったことから、お金の流れを良くするとして「金運・財運」のご利益でも知られます。「弁才天」と書かれることもありましたが、後に財産の「財」の字が使われるようになりました。また、嫉妬深い神様という一面から「縁結び」にもご利益があるとされています。
②特徴と見分け方
弁財天を見分ける最大の特徴は、音楽の神であることを象徴する「琵琶(びわ)」を奏でる美しい女性の姿です。 七福神の中で唯一の女神であるため、すぐに見分けることができるでしょう。
水の神様としての性質から、池や湖、海など水辺に祀られることが多いのも特徴です。有名な鎌倉の銭洗弁天では、境内の湧き水でお金を洗うと金運が上がると言われています。
③由来と豆知識
弁財天のルーツは、インドのヒンドゥー教の女神「サラスヴァティー」です。 サラスヴァティーは、元々はインドに実在した聖なる川の名前が神格化されたもので、流れる川のせせらぎが音楽を連想させることから、音楽や学問、弁舌の女神とされました。
日本に伝わってからは、水の神、農業の神として、また財をもたらす神として多様な信仰を集めるようになりました。その美しさから、多くの芸術作品のモデルにもなっています。
(5)福禄寿
非常に長い頭が特徴的な福禄寿。その名前が示す通り、「幸福」「財産」「長寿」という、人々が願う三つの徳を授けてくれる、とても縁起の良い神様です。
①主なご利益
福禄寿は、その名の通り「福(幸福・子孫繁栄)」「禄(財産・金運)」「寿(健康長寿)」の三つのご利益を兼ね備えています。 この三つの徳は人間が生きていく上で最も大切なものとされ、福禄寿はまさに理想的な人生の象徴と言えるでしょう。
一つの神様をお参りするだけで、これだけ多くの福を授けてくれるのですから、非常にありがたい存在として人々に慕われてきました。
②特徴と見分け方
福禄寿を見分ける最大の特徴は、身体の半分ほどもあるかのような「非常に長い頭」です。 これは、長い年月を生きてきたことによる知恵と徳の高さを象徴していると言われています。
また、豊かな「長い髭」をたくわえ、長寿の象-徴である「鶴」や「亀」を連れていることもあります。手には人々の寿命が書かれた「経典」が結びつけられた杖を持っている姿で描かれます。
③由来と豆知識
福禄寿は、中国の道教で理想とされる「幸福・財産・長寿」を神格化した神様です。 その正体は、南の空に輝く「カノープス」という星の化身である「南極老人星(なんきょくろうじんせい)」とされています。
この星は、見えると寿命が延びると信じられていた大変縁起の良い星でした。福禄寿の長い頭は、この星の精が宿っている証だと考えられています。後述する寿老人と同一神とされる説もあります。
(6)寿老人
福禄寿と同じく、長寿の神様として知られる寿老人。穏やかな笑顔をたたえた老人の姿で、人々に健康で幸せな長寿を授けてくれる神様です。
①主なご利益
寿老人の主なご利益は、文字通り「長寿延命」と「無病息災」です。 いつまでも健康で長生きしたいという、万人の願いを叶えてくれる神様として信仰されています。
また、長寿だけでなく、豊かな暮らしをもたらす「富貴繁栄」のご利益もあるとされています。穏やかで安定した幸せな老後を願う人々にとって、心の支えとなる存在です。
②特徴と見分け方
寿老人は、長寿の象徴である「鹿」を連れている姿で描かれることが多いのが特徴です。 手には、福禄寿と同じく人々の寿命が書かれた巻物を結んだ杖を持っていますが、不老長寿の霊薬とされる「桃」を持っていることもあります。
福禄寿と姿が似ていますが、福禄寿ほどの極端に長い頭ではなく、鹿を連れている点が見分けるポイントになります。穏やかで優しい表情をしています。
③由来と豆知識
寿老人も、福禄寿と同じく中国の道教の神様で、「南極老人星」の化身とされています。 このため、福禄寿と寿老人は元々は同じ神様(同体異説)であり、一つの神格が二人の神様として表現されているという説が有力です。
なぜ二人に分かれたのかは定かではありませんが、人々の願いが多様化する中で、それぞれの徳がより専門化していったのかもしれません。二人の姿の違いを見比べてみるのも面白いでしょう。
(7)布袋尊
大きくはだけた服から立派な太鼓腹をのぞかせ、満面の笑みを浮かべる布袋尊。その姿を見ているだけで、こちらまで朗らかな気持ちになります。
①主なご利益
布袋尊の大きな袋は「堪忍袋」とも言われ、その寛大な心から「夫婦円満」や「家庭円満」のご利益があるとされています。 また、その朗らかな人柄で人々を呼び寄せることから「千客万来」のご利益でも知られます。
子供たちと戯れる姿で描かれることも多く、「子宝」の神様としても信仰されています。布袋尊の笑顔は、日々の小さな悩みを吹き飛ばしてくれるような不思議な力を持っています。
②特徴と見分け方
布袋尊を見分けるポイントは、なんといっても福々しい「大きなお腹(太鼓腹)」と、誰をも幸せにする「満面の笑み」です。 肩に担いだ「大きな袋」もトレードマークです。
この袋の中には、お布施で受け取った宝物が入っており、人々に分け与えるために使われると言われています。その姿から度量が広く、人格者であったことがうかがえます。置物に触れるとご利益があるとも言われています。
③由来と豆知識
布袋尊は、七福神の中で唯一、10世紀頃の中国に実在したとされる禅僧「契此(かいし)」がモデルです。 契此は、常に大きな袋を背負って人々に施しをしていたことから、「布袋」という愛称で呼ばれていました。
彼は優れた予知能力を持ち、人々の吉凶や天候を当てたと伝えられています。その神がかった言動から、人々は彼を56億7000万年後に現れて人々を救うとされる「弥勒菩薩(みろくぼさつ)」の化身だと信じるようになりました。
4. もっと詳しく!七福神にまつわる豆知識と楽しみ方
七福神それぞれの神様について詳しくなると、さらに色々なことが気になってきませんか?ここでは、七福神の知識をさらに深めるための豆知識や、信仰をもっと楽しむためのポイントをご紹介します。
知っていると誰かに話したくなるような面白いトリビアを知って、七福神マスターを目指しましょう。
(1)七福神が乗る「宝船」には何が積まれている?
七福神が乗り、様々な宝物を積んだ「宝船(たからぶね)」の絵は、非常に縁起の良いものとされています。 この絵を正月の夜に枕の下に敷いて寝ると、良い初夢が見られるという言い伝えは有名です。
宝船には、米俵や珊瑚、金銀などの現世利益を象徴する宝物のほか、「隠れ蓑(かくれみの)」や「打ち出の小槌」といった、不思議な力を持つ宝物も積まれています。七福神と宝物が一体となって、私たちに限りない福をもたらしてくれることを象徴しているのです。

(2)正月の風習「七福神巡り」とは?
「七福神巡り」とは、七福神を祀る7つの寺社を巡拝して、一年の福を願う古くからの風習です。 主にお正月の松の内(1月1日~7日、または15日)に行われることが多く、全国各地に様々な七福神巡りのコースがあります。
巡拝する順番に厳密な決まりはありませんが、専用の色紙や御朱印帳が用意されていることが多く、全ての寺社を巡って御朱印を集めるのが楽しみ方の一つです。健康のためのウォーキングも兼ねて、家族や友人と巡ってみてはいかがでしょうか。
(3)これで忘れない!物語で覚える七福神の簡単な覚え方
七福神の名前を覚えるのが難しい、という方のために、簡単な覚え方をご紹介します。例えば、神様たちの特徴を繋げてストーリー仕立てにする方法があります。
「鯛を釣った恵比寿様と、小槌を持つ大黒様が、武士の毘沙門天に宝を届けた。すると琵琶を弾く弁天様が現れ、頭の長い福禄寿と鹿を連れた寿老人が長寿を祝い、最後に布袋様がみんなを笑わせた。」 このように物語にすると、各神様の特徴と名前が繋がり、自然と記憶に残りやすくなります。
(4)実はメンバー交代があった?幻の福の神「吉祥天」と「猩々」
実は、七福神のメンバーは時代や地域によって異なり、現在とは違う神様が含まれていたことがあります。 最も有名なのが、福徳と美を司る女神「吉祥天(きっしょうてん)」です。
吉祥天は弁財天と女神というキャラクターが重なるため、次第に弁財天にその座を譲ったとされています。また、能の演目にも登場する、酒好きの霊獣「猩々(しょうじょう)」が福禄寿の代わりに数えられていた時期もあったようです。七福神の歴史が流動的であったことが分かる、興味深い事実です。
5. 七福神に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、七福神について多くの方が疑問に思う点をQ&A形式で分かりやすくお答えします。これを読めば、あなたの「?」が「!」に変わるはずです。
Q1. 七福神をお参りする順番に決まりはありますか?
厳密な決まりはありません。どの神様からお参りしてもご利益に差はないとされています。
ただし、各地の「七福神巡り」のコースでは、効率よく巡れるようにモデルルートが設定されている場合が多いです。もし専用の色紙などを購入した場合は、そこに示された番号順に巡るのが一般的です。自由に好きな神様からお参りしても全く問題ありませんので、ご自身の関心や都合に合わせて楽しんでください。
Q2. 七福神の中で一番偉い神様は誰ですか?
7柱の神様はそれぞれが異なるご利益と役割を持っており、対等な関係にあります。ただし、絵画や置物では、恵比寿様と大黒天がペアで中央に描かれたり、大黒天が中心に配置されたりすることが多いです。これは、財福や豊穣といった、人々が最も願う現世利益を司る神様として特に人気が高かったためと考えられます。
Q3. 七福神は仏教ですか?神道ですか?
七福神は、仏教、神道、道教など様々な宗教の神様が集まった、日本独自の信仰形態です。
恵比寿様は神道の神様、大黒天・毘沙門天・弁財天は仏教(元はヒンドゥー教)、福禄寿・寿老人・布袋尊は中国の道教や民間信仰に由来します。このように、様々な宗教の神仏を区別なく一緒に祀る「神仏習合」の考え方が根底にあり、特定の宗教に分類することはできません。この寛容さが日本文化の大きな特徴です。
Q4. 寿老人と福禄寿の見分け方は?
最も分かりやすい見分け方は「頭の長さ」と「連れている動物」です。
- 福禄寿:身体の半分ほどもある、極端に長い頭が最大の特徴です。長寿の象徴である鶴や亀を連れていることがあります。
- 寿老人:福禄寿ほど頭は長くなく、穏やかな老人の姿です。同じく長寿の象徴である鹿を連れていることが多いです。
この二柱は元々同じ神様という説もあるため姿が似ていますが、このポイントを押さえれば簡単に見分けることができます。
6. 日々の暮らしに豊かなご利益を迎え入れよう
この記事では、七福神の名前一覧から、それぞれの神様のご利益、特徴、知られざる由来や豆知識まで、網羅的に解説しました。
七福神は、インド、中国、日本という異なる国の神様たちが、日本の大らかな文化の中で一つにまとまった、福をもたらすスーパーチームです。商売繁盛の恵比寿様、財福の大黒天、勝負運の毘沙門天、芸術の弁財天、そして長寿を司る福禄寿と寿老人、家庭円満の布袋尊。それぞれの神様の背景を知ることで、より深く、親しみを持って信仰することができるでしょう。
この記事をきっかけに、ぜひお近くの七福神を祀る寺社を訪ねてみてください。神様たちの物語に思いを馳せながらお参りすれば、きっとあなたの毎日に豊かな福が舞い込んでくるはずです。
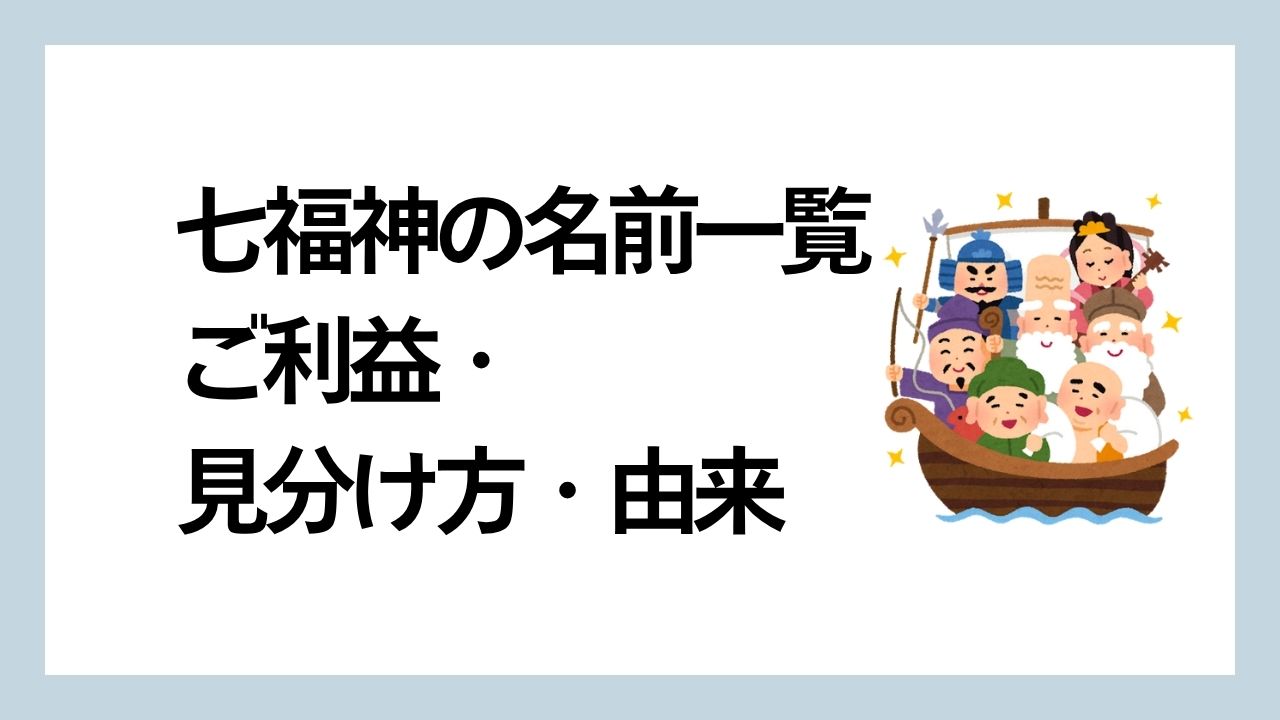
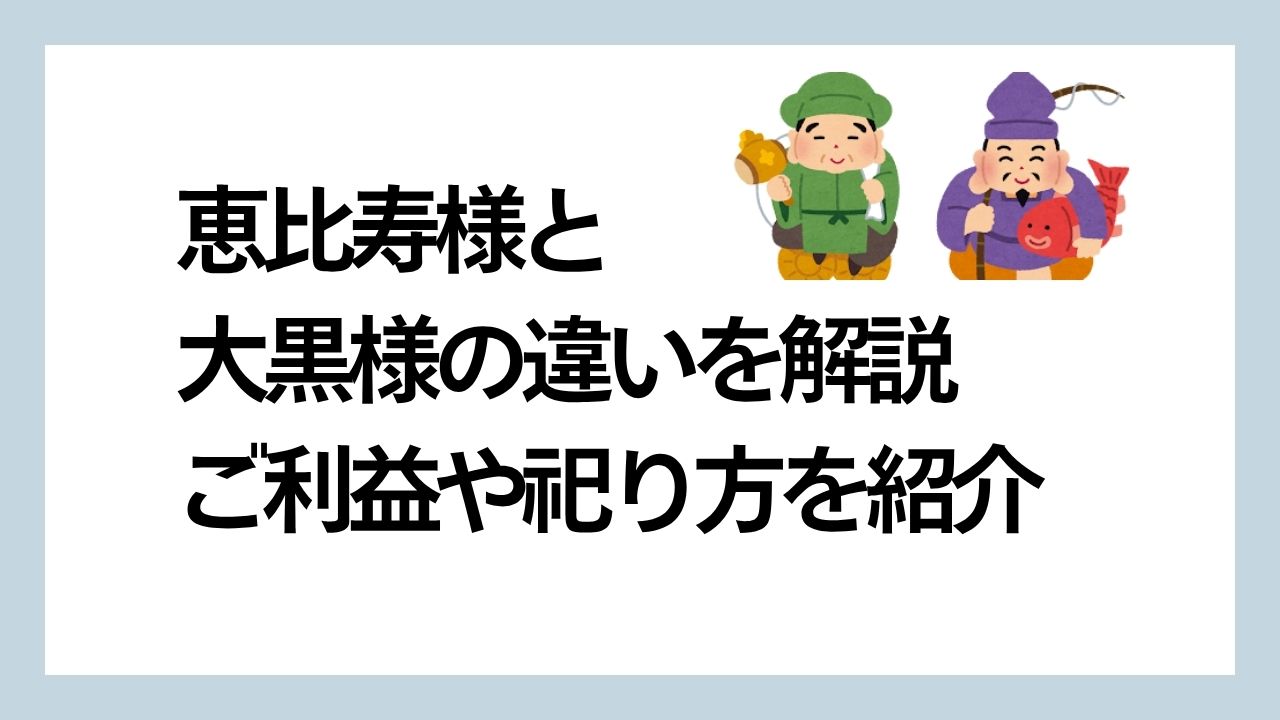
コメント