毎年7月、京都の夏を彩る祇園祭。千年以上の歴史を持つこの祭りは、日本三大祭りの一つに数えられ、多くの人々に親しまれてきました。
そんな祇園祭の風物詩のひとつに、「ちまき」があります。ちまきと聞くと、端午の節句に食べる笹に包まれた餅菓子を思い浮かべる方も多いでしょう。
しかし、祇園祭のちまきは食べ物ではありません。では、祇園祭のちまきとはいったい何なのでしょうか。なぜちまきが飾られ、厄除けのお守りとして人々に大切にされてきたのでしょうか。
この記事では、祇園祭のちまきの意味や歴史、飾り方、そして地域の人々の思いにまで迫り、民俗学的視点も交えて詳しく解説していきます。
祇園祭とちまきの関係
祇園祭とちまきの関係を紐解くには、まず祇園祭そのものがどんな祭りなのかを知る必要があります。
京都の歴史と人々の暮らしに根ざした祇園祭の成り立ちを知ることで、ちまきがどのようにして人々の生活に浸透してきたのかが見えてきます。

祇園祭の概要
祇園祭は、京都市東山区に鎮座する八坂神社の祭礼です。起源は平安時代の869年、当時、京の都で疫病が大流行した際、御霊会(ごりょうえ)を行い、66本の鉾を立てて神を鎮めたことが始まりとされています。
以来、疫病退散や無病息災を願う祭りとして受け継がれ、現在では7月1日から31日まで、一か月にわたって多彩な行事が催されます。
中でも、街を練り歩く山鉾巡行は「動く美術館」と称され、国内外から多くの観光客を集める一大イベントです。祭り全体を通じて、京都の町衆が中心となり運営しており、地域に深く根づいた信仰行事であることも祇園祭の特徴です。
ちまきが売られている理由
祇園祭の期間中、山鉾町では「厄除けちまき」が販売されます。これは、祇園祭がそもそも疫病除けを願う祭りだったことと深く関係しています。
ちまきは、厄災や疫病を家に寄せ付けないためのお守りとして飾る風習が、江戸時代にはすでに定着していたとされます。
各山鉾町がそれぞれのちまきを売り出し、その収益は山鉾の維持費や地域活動の支援にあてられています。こうした仕組みは、祇園祭が町衆の手によって守られてきた歴史を今に伝える象徴でもあるのです。
ちまきの由来と意味
祇園祭のちまきが「厄除け」の象徴として人々に受け入れられてきた背景には、古代中国から伝わった伝承と、日本独自の風習が融合した歴史があります。
ここでは、ちまきが持つ意味や由来について、さらに詳しく見ていきましょう。

中国から伝わったちまき伝説
ちまきのルーツは、中国戦国時代の詩人・屈原(くつげん)の伝説にあります。国を憂いて川に身を投げた屈原の遺体が魚に食べられないよう、村人たちが米を笹で包んだものを川に投げ入れたのが、端午の節句にちまきを供える風習の起源といわれています。
このちまきは悪霊や厄災を遠ざける象徴とされ、中国各地で厄除けの意味を持つようになりました。日本にもこの習俗が伝わり、特に端午の節句にちまきを食べる風習として広がっていきました。
そして、疫病退散を願う祇園祭においても、ちまきは災厄を払う力を持つものとして、次第に飾るお守りへと変化していったと考えられています。
祇園祭のちまきの意味
京都の祇園祭で売られているちまきは、食用ではなく、笹で包まれたお守りです。
中身は藁などで作られており、玄関や家の門口に飾ることで、その家に災厄や病が入ってこないようにする魔除けの役割を果たすといわれています。
これは、八坂神社のご祭神・スサノオノミコトが疫病神を退けたという神話とも重なり、人々の無病息災への願いを託した習慣となりました。食べ物ではなく「護符」としてのちまきは、祇園祭ならではの風習といえます。
八坂神社とスサノオノミコトについて詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。
笹で巻いているのはなぜ?
笹の葉は、古くから日本各地で神聖な植物とされ、魔除けや浄化の力があると信じられてきました。
笹には防腐作用もあり、清らかさの象徴でもあります。そのため、ちまきを笹で巻くことで、より強い「けがれを払う」力を持つと考えられてきたのです。
こうした自然物の信仰は、民俗学の世界でもさまざまな地域で報告されており、人々の暮らしと深く結びついた民間信仰のひとつといえるでしょう。
ちまきの飾り方と時期
ちまきはただ買うだけではなく、正しい場所に飾ることや、適切な時期に飾ることで本来の力を発揮するといわれています。ここでは、ちまきの飾り方や処分方法について詳しく解説します。

いつどこに飾るべき?
ちまきは、購入後なるべく早く家の玄関や門に飾るのが一般的です。これは、外からやってくる厄災や疫病を家の中に入れないための「結界」としての意味を持つためです。
飾る時期に厳密な決まりはありませんが、祇園祭が行われる7月中に飾り、そのまま一年間掛けておく家庭が多いです。
家の玄関にちまきを飾ることは、「この家は神の加護を受けている」という印にもなり、町内のコミュニティにとっても大切な風景の一つです。
古いちまきの処分方法
一年間家を守ってくれたちまきは、次の祇園祭の頃にお焚き上げをして処分するか、八坂神社へ返納するのが一般的です。
八坂神社では、古いお札やお守りとともに感謝を込めて焚き上げる神事が行われています。
民俗学的には、役目を終えた護符を自然へ戻すという行為は、古来より「魂を鎮め、再び循環させる」意味があるとされ、神聖視されてきました。
山鉾ごとのちまきの違い
ちまきは、すべて同じように見えて、実は山鉾町ごとに異なる顔を持っています。ここでは、それぞれの山鉾のちまきに込められた意味や特色を知ることで、さらに祇園祭の深い魅力に迫ってみましょう。

山鉾町ごとの特色
祇園祭の主役ともいえる山鉾は、三十数基あり、それぞれに由来や守護神、装飾のテーマが異なります。そして、各山鉾町が販売するちまきにも、その山鉾にまつわる言い伝えや守護の願いが込められています。
たとえば、「長刀鉾」のちまきは特に有名で、疫病神を追い払う力が強いと信じられ、毎年多くの人が求めに訪れます。
また、「菊水鉾」のちまきは、家内安全や商売繁盛を願うものとして親しまれており、護符のデザインや紐の色も山鉾によって微妙に違うため、コレクターのように毎年集める人もいるほどです。
人気のちまきは?
中には、数量限定のちまきを出す山鉾もあり、人気のちまきには早朝から行列ができることも珍しくありません。とくに初日や山鉾巡行の日は、多くの人が買い求めに訪れます。
京都の地元の人にとっては、毎年お気に入りの山鉾のちまきを手に入れ、家を守ってもらうということが夏の恒例行事であり、信仰心と暮らしが一体となった大切な時間です。
現代に残るちまき文化
時代が変わり、人々の生活様式も大きく変化してきましたが、祇園祭のちまき文化は現代においても力強く息づいています。
ここでは、観光客にとってのちまきの意味や、地域の人々にとってのちまきが持つ価値を見ていきます。

観光客へのお守りとしての役割
祇園祭を訪れた観光客の多くは、ちまきをお土産として持ち帰り、玄関や部屋に飾ります。それは単なる旅の思い出ではなく、「無病息災」「家内安全」という願いが込められた護符としての役割も担っています。
ちまきを買い求める体験そのものが、京都という古都に触れ、千年以上受け継がれてきた祈りの文化を感じる瞬間でもあります。
京都の暮らしとちまき
京都に暮らす人々にとって、ちまきは「生活の一部」であり、「町内のつながりを確かめ合う象徴」でもあります。
祭りの時期になると、近所の人同士で「今年はどの山鉾のちまきを買ったのか」と話題にしたり、ちまきを持って町を歩く人の姿を見かけると、夏の到来を感じるという声も聞かれます。
こうした風景は、ただの行事ではなく、京都の町が一体となって長い年月守り伝えてきた暮らしの文化なのです。
まとめ
祇園祭のちまきは、千年以上にわたる歴史と、疫病退散・無病息災を願う人々の強い祈りが込められた大切なお守りです。
笹や藁といった自然素材に、神聖な力が宿ると信じ、家を守るために玄関先に飾る習慣は、京都の人々が暮らしの中で育ててきた信仰の形でもあります。
ちまきの文化は、山鉾町ごとに少しずつ異なる顔を持ち、町衆が自分たちの誇りとして受け継いできました。そこには「厄を払いたい」「大切な家族や町を守りたい」という願いがあり、私たちが現代でちまきを手に取る時にも、その思いは確かに続いています。
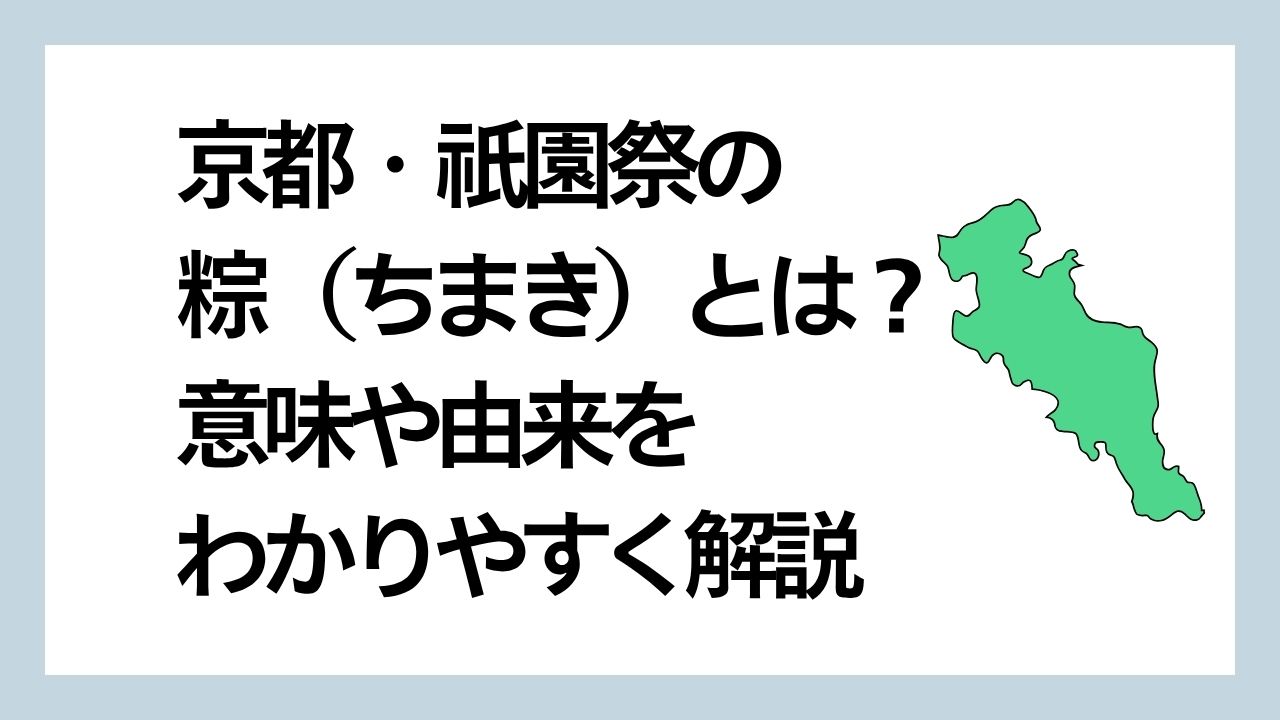
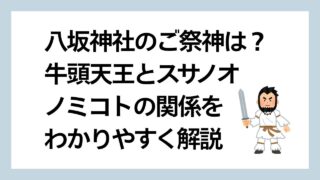
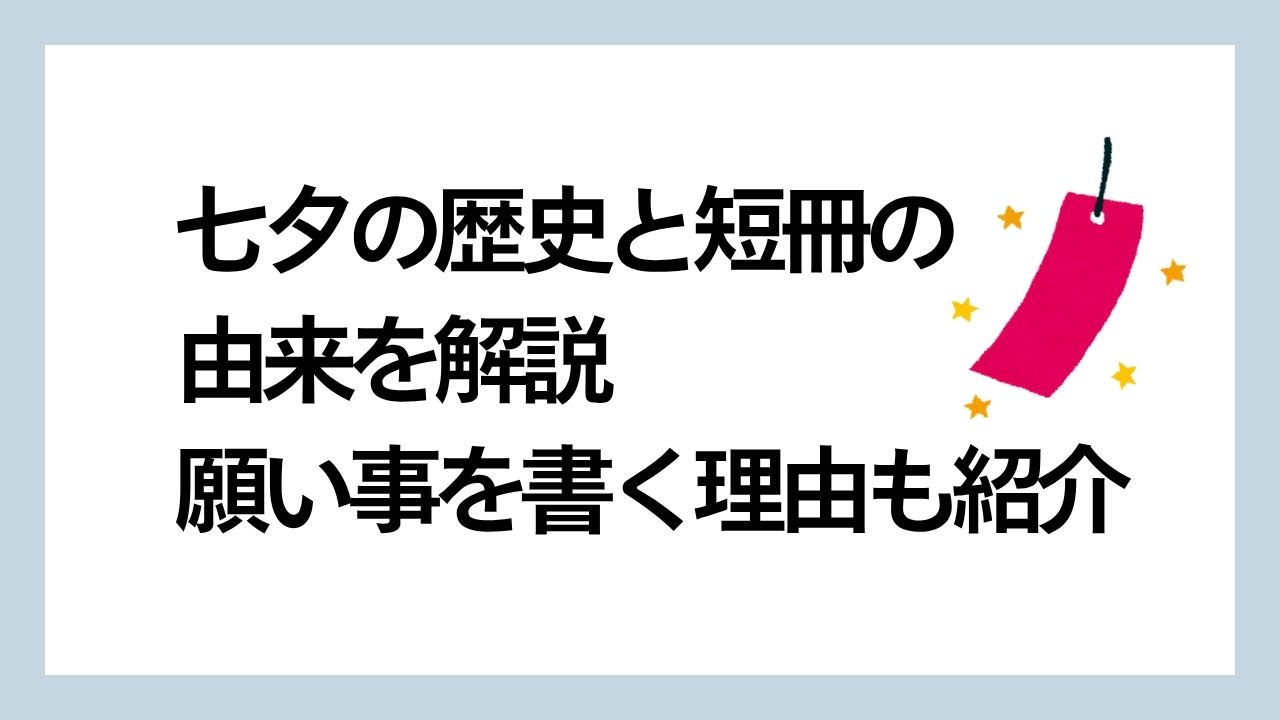
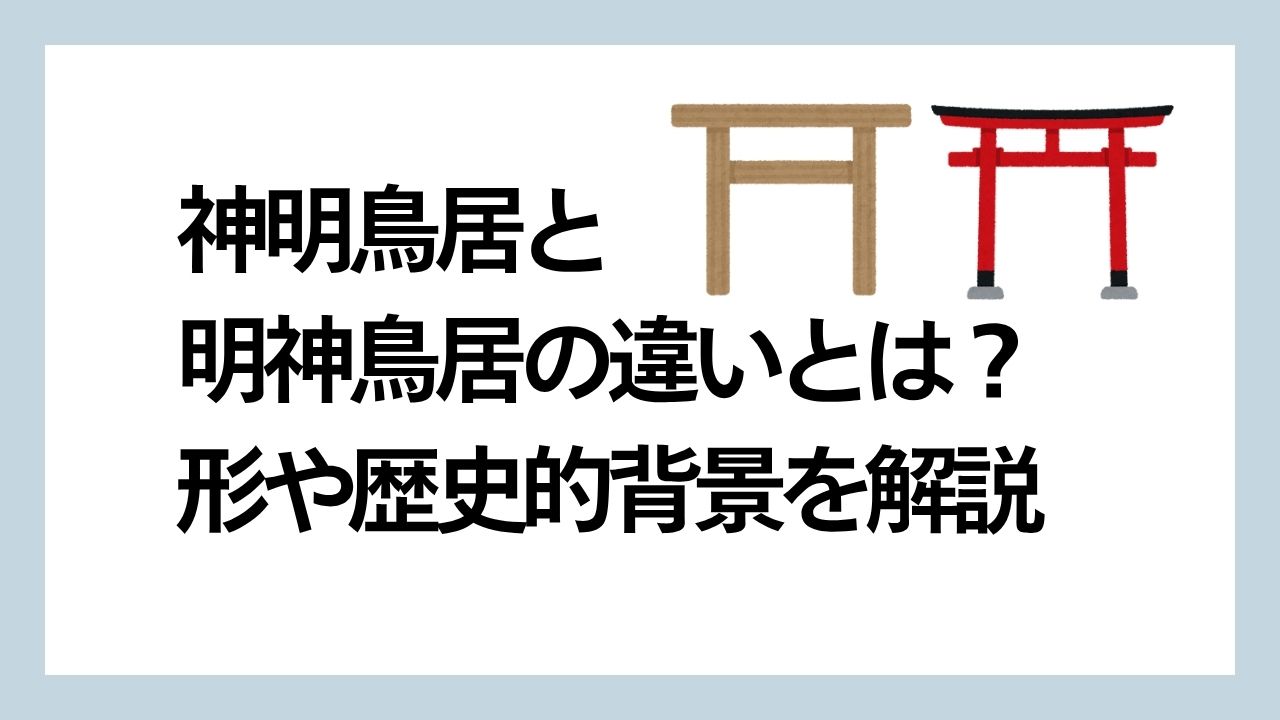
コメント